熟慮期間以降の相続放棄について
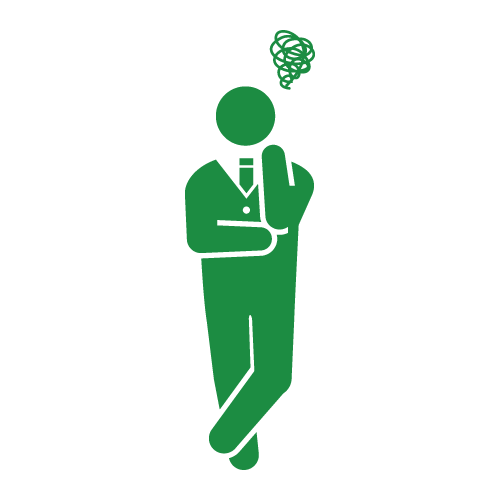
ちょっと前に、「モーニングショー」というTV番組で、 相続コーディネーターと名乗る方が、7月1日からの相続法の大改正について説明された内容について、「誤りなのでは?」との反響が多く寄せられたようです。
直接、私は拝見していないのですが、 借金や負債等、相続することで損をするマイナス遺産に関して、「(気づいてから)3カ月以内なら相続放棄できる」、「相続後にマイナス遺産が見つかっても放棄できない」、「(相続しようと思ったら)すぐに財産の確認から入ります。3カ月というのはその期間で十分だろうという時間なんです」、「(マイナスだけ相続するのは)なしです。0か100か、ですよね」等々ご説明されていたとのこと。
私自身、例外があることは知ってましたが、その辺りの話になると、相続に詳しい司法書士の先生に対応をお願いするので、今回は少しその辺りについて、細かいところを記したいと思います。
1.相続放棄について
まずは、これまでの相続放棄に関する記事について
相続の3つの方法について
相続放棄の期限について
父の借入金が多いときの相続放棄について
相続放棄とは、簡単に言えば「相続人ではなくなる」手続きであり、 被相続人のすべての相続財産(プラスの財産とマイナスの財産の全部)を相続せずに、最初から相続人ではなかったとみなされます。
すなわち、相続人ではなくなりますので、不動産や預貯金と言ったプラスの財産を相続する事はできなくなりますが、借金等のマイナスの財産も相続しなくても済むということです。
そして相続放棄は、「自分のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内」に行う事が原則です(民法第915条)。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3452
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
この「自分のために相続の開始を知った時から三ヵ月以内」を「熟慮期間」と言い、一般的には被相続人が亡くなった事、自分が相続人である事を知った時から三ヶ月なのです。
ただし、この原則を前提にすると、テレビでも話題になっていように、 「被相続人が亡くなって三ヶ月経過に被相続人に借金がある事が分かった場合」など、 相続人に不利益になるケースがあります。
このような場合、被相続人が亡くなったことを知った三ヵ月以内に、相続を放棄しなかった。すなわち、原則として相続人がその借金を支払う義務があるのです。
しかし、被相続人が沢山の財産(遺産)を残してくれていた場合は良いですが、そうではない場合、相続人自身のお金で支払う必要が出てきますし、借金の額によっては、相続人が破産など不利益を被る可能性もあります。そのため、相続放棄の実務ではこの「三ヶ月」について、柔軟な対応を行っています。
2.三ヵ月経過していても相続放棄が出来るケース
まず初めに、最高裁判例のこちらをご覧ください。 ※判例:最高裁判所昭和59年4月27日
裁判の要旨は以下の通りです。
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
ポイントとしては、
- 相続人は、被相続人に財産が全くないと信じていたこと。
- その事実を信じることに正当な理由が相続人にあったこと。
- 被相続人との関係、その他の事情により相続財産の調査をすることが困難となる事情があった。
以上、この裁判は、「相続人が相続財産(マイナスの財産も含む)の存在を知った時から三ヶ月はスタートする 」 と判断されました。家庭裁判所もこの判例を踏まえ、三ヶ月について柔軟な取扱いがされているのです。 しかし、これはあくまでも例外的な措置となりますので、そのあたりは十分に注意する必要があります。
そして、他にも家庭裁判所への申述により、例外的に相続を知ってから三ヵ月以降に相続放棄を認められる可能性もあるので、まずはそのような状況に陥ったとしても、自らの知識だけで判断せずに、落ち着いてなるべく早く、専門家に相談することが大事になります。
3.その他、熟慮期間の伸長とその申立て方法について
今回の話とは、少しずれますが、三ヵ月以内である熟慮期間も申し立てにより、伸長してもらえる場合もありますので、以下に記します。
再度、民法第915条です。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
tps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3452
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
相続放棄の熟慮期間の伸長は、利害関係人又は、検察官の請求によって、家庭裁判所に対して申立てることにより認められ、相続財産の全ての調査、相続財産全ての把握が3カ月では間に合わないような場合に行います。
例えば、相続財産の内容が、預貯金ばかりの相続財産だと、把握をするにはそんなに時間はかからないと思いますが、不動産や株式(特に非上場株式)などの金銭でない物の場合、、価格の鑑定をしないと、どれくらいの金銭(価値)になるか分からない場合があります。このようにプラスの財産の価格がすぐに判明しないような場合だと、マイナスの財産と比較することが出来ず、相続放棄をしなければいけないのか、また相続を承認しても大丈夫なのか、判断するまでに時間がかかります。
また、不動産などは相続路線価と取引相場の乖離なども多く、実際に査定をしてみないと分からない場合もあり、調査に時間がかかる可能性が高いです。このような場合、熟慮期間が3カ月では、相続放棄の判断をするには期間が足りない恐れがあります。こういった場合に家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の申立てることになります。
相続の承認又は放棄の期間の伸長
1. 概要
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
- 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
- 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
- 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
2. 申立人
- 利害関係人(相続人も含む。)
- 検察官
3.申立先
相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら
4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分(相続人1人につき)
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください)。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書(7の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
3. 伸長を求める相続人の戸籍謄本
【被相続人の配偶者に関する申立ての場合】
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)に関する申立ての場合】
4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. その他
申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
裁判所HP:相続の承認又は放棄の期間の伸長
またまた話がずれますが、今回の 「モーニングショー」 の誤った情報発信、相続コーディネーターさんも、テレビ局も発信する情報の確認など、事前の準備が不足していたのではないかと思います。コメンテーターさんからの質問も想定問答にしておいて、視聴者に正しい情報を分かりやすくしておくのが正解だったかなと思います。
相続に関するお仕事を包括する国家資格がない現状、民間で相続に関するさまざまな資格があります。しかしながら、どの立場からでも、情報発信をする立場として、誤った情報を発信して、その誤りを信じた方が残念な結果にならないようにしなければならないと感じました。
これからも、丁寧かつ正確な情報発信で、相続にお悩みのお客様のお手伝いが出来ればと当事務所は考えています。今後も相続にお困りのお客様は、福岡市東区の香椎相続不動産事務所へお気軽にお問合せください。
これまでの相続放棄に関する記事
相続の3つの方法について
相続放棄の期限について
父の借入金が多いときの相続放棄について
知らないと後悔する、後から知って後悔する
相続・事業承継に関する最新の事例・情報を定期配信中!
お友達登録で、
「誰もが知ってるあの人も?
読んで知って実感する。
身近な相続トラブル事例集」
無料プレゼント中!


